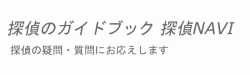離婚問題を弁護士に依頼した費用の相場を紹介
離婚をする際には夫婦間で様々な取り決めを行う必要があります。
しかし、夫婦の話し合いで合意が難しいときには、弁護士の利用を検討する人も多いと思います。
弁護士の利用を検討したときに最も心配なのは、弁護士を利用する費用ではないでしょうか?
日常生活で弁護士を利用する機会は少ないですし、弁護士は費用が高いと聞いた人も多いと思います。そのため、弁護士の費用に不安を感じるのも仕方がないのかもしれません。

離婚問題を弁護士に依頼した費用の相場を紹介
弁護士は慰謝料の請求や離婚問題など、依頼内容により定額で利用できる料金体系ではありません。着手金、成功報酬金、実費など複数の料金が組み合わさった契約が一般的で、始めて利用する方には総額が分かり難い料金体系です。
また、希望する結果が得られなくても一定の費用が必要で不安を感じる人も多いようです。
弁護士費用は全ての弁護士が同じの料金で利用できる訳ではなく、弁護士が独自に料金を決めているので弁護士により料金が異なる特徴もあります。
弁護士費用の相場が分かれば、弁護士に依頼をするのか判断の参考にできますし、弁護士料金に対する不安も解消できるでしょう。
このページでは、浮気の慰謝料や離婚問題を弁護士に依頼したときの費用の相場を紹介します。
❏【 目 次 】 離婚問題を弁護士に依頼した費用の相場を紹介
1 弁護士の料金体系
1-1 弁護士により料金が異なる
1-2 5つの意味を持つ費用がある
1-3 具体的な弁護士費用の計算方法
2 弁護士費用の相場
2-1 相談のみをしたときの弁護士費用の相場
2-2 書類の作成を依頼したときの弁護士費用の相場
2-3 離婚問題を依頼したときの弁護士費用の相場
2-4 慰謝料を請求したときの弁護士費用の相場
2 弁護士費用は高い?
3-1 弁護士の業務にはコストが掛かる
3-2 弁護士は高所得な職業?
3-3 結果が出れば高いとは言えない?
3-4 弁護士を利用するメリットも多い
1 弁護士の料金体系
弁護士費用の相場を知る前に、先ずは弁護士の料金体系を理解する必要があります。
弁護士には複数の料金体系があり、着手報酬金制、タイムチャージ制、顧問契約の3つの料金体系が中心です。この中で、一般の人が弁護士を利用するときには、着手報酬金制が最も一般的な料金体系です。
着手報酬金制は、弁護士に依頼をした時点で着手金を支払い、結果に対して別途成功報奨金を支払う料金体系です。また、弁護士が活動をする際に必要な、実費や日当の経費が別途必要です。
離婚問題や慰謝料請求で基本となる料金体系で、和解や裁判など解決方法に関わらず利用される料金体系です。
この料金体系は、弁護士と依頼者の双方にメリットがあり最も合理的な料金体系でもあります。
タイムチャージ制の料金体系は、弁護士を時間単位で利用するときに使われます。弁護士への法律相談や和解交渉の同席など、一定時間弁護士を拘束する必要があるときに利用される料金体系です。
1時間に付き幾らの料金で弁護士を利用でき、料金体系が明確で分かりやすいメリットがあります。ただし、希望する結果が出ても出なくても同一の料金が必要な料金体系です。
顧問契約とは、月々一定金額を支払い法務全般を弁護士に依頼する際に用いられる料金体系です。優先的に依頼を受けてくれたり、一部の業務を無料や低料金で利用できる契約もあり、定期的に弁護士を利用する機会がある企業が主に利用する料金体系です。
離婚や慰謝料の請求は単発の依頼なので、顧問契約で弁護士を利用するケースはほとんどないと思われます。
弁護士の料金体系は、下記のページで紹介していますのでご確認ください。
1-1 弁護士により料金が異なる
平成16年までの弁護士費用は、日本弁護士連合会が定めた弁護士報酬基準で決めらており、原則として全ての弁護士が同じ料金となっていました。
しかし、現在では弁護士報酬基準が撤廃され各弁護士が自由に報酬の額を決めています。つまり、現在では弁護士により料金が異なります。
規制が緩和された現在でも、旧弁護士報酬基準を参考に料金を決めている弁護士が多いですが、独自に料金を決めている弁護士も増えてきています。
利用者には選択肢が増えるメリットがあるのですが、弁護士を選ぶときに迷ってしまう人も居るようです。
1-2 5つの意味を持つ費用がある
弁護士を利用したときの費用は、一つの依頼であっても複数の意味を持つ費用が発生し合計が支払総額です。
主に、5つある弁護士費用の特徴を説明します。
弁護士費用は、主に次の5の意味を持つ料金で構成される。
・相談費用(弁護士に法律相談をする際に必要な費用)
・着手金(弁護士に依頼する時点で必要な費用)
・成功報酬金(結果に対して発生する費用)
・日当(弁護士を拘束するときに必要な費用)
・実費(交通費、宿泊費、印紙代の経費)
相談費用(弁護士に法律相談をする際に必要な費用)
弁護士に法律相談をするときに必要な費用です。
弁護士から法的なアドバイスを受けたり法律に関する相談ができます。
弁護士へ相談をしたからといって必ず依頼する必要はありません。法律相談だけで問題が解決できる場合もありますし、相談の結果で依頼するかしないのかを決めることができます。また、複数の弁護士に相談をして、自分に合った弁護士を見つける人も多いようです。
弁護士を利用する際には初めに相談をすると思いますので相談費用が発生します。ただし、その弁護士を利用した場合には、相談費用を取らない弁護士もあるようです。
着手金(弁護士に依頼する時点で必要な費用)
着手金は、弁護士に依頼をする際に前払いで支払う費用です。
結果が希望通りに「終わった・終わらなかった」に関わらず支払う必要がある費用です。希望通りの結果が得られなかったときや途中で依頼を辞めたときでも返金はされません。
着手金は依頼内容により金額が異なり、和解が成立せず調停や裁判に進むと別途着手金が必要になる契約が一般的です。
成功報酬金(結果に対して発生する費用)
成功報酬金は、契約した結果が出たときに支払いが必要な費用です。契約した結果が出なければ支払う必要はありません。
複数の依頼がある場合には、それぞれに成功報酬金を設定し結果が出た依頼に対して支払う必要があります。
一般的には、金銭的なメリットがある依頼には受け取った金額の〇〇%、金銭的なメリットがない依頼には一律○○万円と決めます。
日当(弁護士を拘束するときに必要な費用)
出張が必要な場合や弁護士を拘束するときに必要な費用です。
調停や裁判は相手の居住地の裁判所で行う必要がありますが、相手が遠方に住んでいると弁護士の日当が必要になる場合がります。
また、弁護士と相手が直接会って交渉を行う場合にも、相手が遠方に住んでいると日当が必要な場合があります。
実費(交通費、宿泊費、印紙代の経費)
弁護士が仕事を行う上で実際に支払った交通費、宿泊費、印紙代、切手代などの諸経費を実費といいます。
弁護士に業務を依頼した場合には、活動に必要な実費が別途必要な契約が一般的です。
1-3 具体的な弁護士費用の計算方法
弁護士を利用するときには、弁護士への相談をしてから依頼をするかを決めますので相談費用が必要です。
複数の弁護士に相談して利用する弁護士を決めるときには、相談をした弁護士の人数分の相談費用が発生します。
一部の弁護士では、初回の相談費用を無料にしていたり依頼すると無料になる場合もあるようです。
弁護士を利用するには前払いの着手金が必要です。
着手金は、希望する結果が出なかったり途中で依頼を取り辞めても戻ってくるお金ではありません。
また、和解での解決を目指していたが和解が成立せず調停になると、新たに調停に対する着手金が必要です。調停が不成立となり裁判を行うときも、裁判に対する新たな着手金が必要です。
着手金は一度支払えば解決するまで対応してくれるのではなく、調停や裁判が必要になると新たな着手金が必要です。
弁護士が活動するときに必要な経費は、依頼者が負担する料金体系が一般的です。
出張が必要なときの交通費、宿泊費、裁判者に支払う印紙代、調書の謄写代が別途必要です。
契約した結果が出たら、契約時に決めた成功報酬金の支払いが必要です。
成功報酬金は、離婚の成立で○○万円、親権の獲得で○○万円、慰謝料は利益の○○%と、個別に設定する契約が一般的です。依頼内容が多ければ成功報酬金の合計金額も増えます。
合計金額が弁護士費用の総額
全ての料金を合計した金額が弁護士費用の支払総額です。
依頼内容(離婚、慰謝料、親権、財産分与、養育費)が多ければ支払総額が多くなり、経済的利益が多い場合も支払総額は増えます。
また、和解で成立すれば弁護士費用は比較的安く済みますが、調停や裁判を行うと弁護士費用は高くなる傾向があります。
2 弁護士費用の相場
弁護士費用の合計額は依頼する内容や条件で変わります。また、和解で合意できるのか、調停や裁判が必要かによっても変わります。
弁護士費用の目安となる料金相場を紹介しますので一つの目安としてください。
2-1 相談のみをしたときの弁護士費用の相場
弁護士は、和解交渉や裁判の代理だけが業務ではなく、法律相談や法律に関するアドバイスも行っています。
離婚する際には、弁護士に財産分与、親権、養育費、面会交流などに関する法的なアドバイスが受けられます。また、浮気相手への慰謝料が獲得できるのか、慰謝料請求の方法や注意点、事前の対策、証拠の集め方の相談もできます。
弁護士への相談だけで問題が解決できれば、弁護士費用は相談料のみでありそれほど必要ありません。
弁護士への相談費用は、1時間に付き5,000円~15,000円が相場です。
弁護士のアドバイスを基に話し合いを行い、必要と感じたら弁護士へ依頼をする人も多いようです。
2-2 書類の作成を依頼したときの弁護士費用の相場
離婚条件でお互いに合意ができている場合でも、後になりトラブルが発生しないために合意内容を書面として残すことが大切です。
財産分与や慰謝料などを既に受け取っており親権も確定していれば、問題が解決しているので書面を作成する重要性は低いかもしれません。
一方で、約束した金銭をまだ受け取っていない、養育費を長期間に渡り受け取る、面会交流の約束がある場合には、書面を作成しておかないと合意内容を証明できなくなってしまいます。
離婚協議書や公正証書は当事者でも作成できますし、弁護士が作成しても効力が強くなる訳ではありません。
しかし、弁護士が作る書類は誤りがなく細かな部分まで考えて作られており、後々のトラブルを避けられるメリットがあります。
既に夫婦間の取り決めが合意できており、離婚協議書の作成のみであれば5万円~10万円程度の金額が相場です。
また、離婚協議書を基に公正証書の作成を弁護士に依頼すると、別途5万円程度の手数料が必要になるようです。
書類の作成だけであれば弁護士費用は比較的少額で利用できます。
2-3 離婚問題を依頼したときの弁護士費用の相場
協議で解決できた場合
協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚を成立させる離婚方法ですが、この話し合いを弁護士に代理して貰うことができます。
調停や裁判と比べ手続きが簡素で弁護士費用も安く、離婚の成立だけが目的なら着手金は10~20万円、成功報奨金は10~20万円が相場です。
ただし、夫婦の話し合いで合意できない原因があるはずで、親権、財産分与、慰謝料、養育費の合意ができていなければ、これらの交渉も弁護士に依頼しなければ離婚の合意はできません。
複数の交渉を弁護士に依頼すると着手金が増額され、着手金の合計は10~30万円程度になるようです。
また、成功報酬金は、親権の獲得は10~20万円、財産分与は獲得金額の10~20%、慰謝料は獲得金額の10~20%、養育費は2~5年間で受け取る金額の10%前後が相場です。
相手が遠方に住んでおり弁護士の出張が必要な場合には、実費や日当が別途発生する場合もあります。
また、公正証書の作成を弁護士に依頼する場合には別途費用が必要です。
全ての費用を含めると、協議離婚を弁護士に依頼した費用の総額は、30万円~60万円程度になる場合が多いようです。
調停で解決できた場合
調停は裁判所で行う話し合いの場であり、法的な拘束力を持つ判決は出せません。また、原則非公開で行われるなど裁判とは異なる制度です。
調停離婚とは、夫婦の間に調停委員が入り話し合いを進める制度で、弁護士を利用せずに本人のみでも進められます。
ただし、調停委員はあなたの見方をしてくれる存在ではなく、あくまでも中立の立場で話し合いを進める役割を担います。調停での話し合いを有利に進めるため、弁護士に依頼をする人が多い傾向があります。
調停離婚は協議離婚と比べると時間や手間が掛かるので、弁護士費用もやや高くなり離婚の成立だけが目的なら着手金は20~30万円、成功報奨金は20~30万円が相場です。
ただし、親権、財産分与、慰謝料、養育費など、合意できない問題も弁護士に依頼しなければ解決できないケースが多いです。
複数の交渉を弁護士に依頼すると着手金が増額され、着手金の合計は20~40万円程度になるようです。
また、成功報酬金は、親権の獲得は10~20万円、財産分与は獲得金額の10~20%、慰謝料は獲得金額の10~20%、養育費は2~5年間で受け取る金額の10%前後が相場です。
相手が遠方に住んでおり弁護士の出張が必要な場合には、実費や日当が別途発生する場合もあります。
その他にも、調停は家庭裁判所に収める印紙代や切手代が4,000円前後が必要です。
全ての費用を含めると、調停離婚を弁護士に依頼した費用の総額は、40万円~80万円程度になる場合が多いようです。
裁判まで行った場合
裁判離婚とは、夫婦間で離婚そのものや離婚条件の合意ができない場合に、裁判所の判決で強制的に結論を出す離婚方法です。
裁判の判決には法的な拘束力があるので必ず結論がでるメリットがあります。しかし、あなたの希望する結果が得られなくても、裁判所の判決には従う必要があります。
また、裁判は一度判決が出るとやり直しができないので、事前に十分な準備をして進めなければなりません。
離婚訴訟は弁護士を利用せず本人でも裁判を行えますが、一般的に法律の知識がある弁護士を利用する人が多いようです。弁護士を利用せず裁判を行うと時間や手間が必要ですし、適切な主張や対策ができず不利になってしまう場合もあります。
裁判離婚は、手続きが複雑で結論が出るまでに時間が掛かります。また、弁護士は事前に多くの準備をして裁判に挑みますので、弁護士費用も協議離婚や調停離婚と比べて高くなります。
離婚の成立だけを目的に弁護士に依頼した場合には、着手金は20~30万円、成功報奨金は20~30万円が相場です。
夫婦間で合意できない内容があるから裁判になるはずで、合意できない内容も弁護士に依頼するケースが一般的です。親権、財産分与、慰謝料、養育費なども依頼すると、着手金が増額され合計は20~40万円が相場です。
また、成功報酬金は、親権の獲得は10~20万円、財産分与は獲得金額の10~20%、慰謝料は獲得金額の10~20%、養育費は1年で受け取る金額の10%前後が相場です。
その他、切手代、調書の謄写代、印紙代が別途必要で、合計すると最低でも数万円の費用は必要です。
全ての費用を含めると、裁判離婚を弁護士に依頼した費用の総額は、60万円~120万円の間になる場合が多いようです。
2-4 慰謝料を請求したときの弁護士費用の相場
和解で解決できた場合
浮気の慰謝料は損害賠償の一種ですので、弁護士費用も基本的には損害賠償の請求と同じです。
損害賠償請求は当事者が合意できれば成立するので、弁護士を利用せず本人で交渉を行い解決ができます。
しかし、個人で交渉を行っても相手が交渉に応じなかったり、トラブルになってしまうリスクがあります。
弁護士に依頼するとトラブルになるリスクがなく、交渉がスムーズに進む可能性が高いメリットがあります。また、話し合いのストレスから解放されたり不安が少なくなるなど、精神的なメリットもあるようです
慰謝料の和解交渉を弁護士に依頼した場合には、着手金は10~20万円、成功報奨金は獲得金額の10~20%が相場です。
弁護士の和解交渉は、内容証明郵便でやり取りする方法が一般的です。この場合は切手代が別途必要ですが、数千円程度で収まるケースが多いようです。
相手と会って交渉を行う場合には、相手が遠方に済んでいれば交通費や宿泊代、日当が別途必要になる場合もあります。
調停で解決できた場合
浮気の慰謝料請求は、調停を利用した話し合いで解決を図る方法が可能です。
調停は調停委員を通じた話し合いで紛争を解決する手続きで、裁判とは異なり法的拘束力を持った判決は出せません。しかし、調停は話し合いがスムーズに進み合意できる場合もあるようです。
ただし、慰謝料請求は調停では解決しない場合が多く、調停を行わず裁判で慰謝料を請求する方法が一般的に取られます。
慰謝料の調停を弁護士に依頼した場合には、着手金は10~20万円、成功報奨金は獲得金額の10~20%が相場です。
調停は相手の居住地で行う必要があるので、実費や日当が発生する場合があります。
また、調停は家庭裁判所に収める印紙代や切手代が必要ですが、4,000円前後で収まるケースが多いようです。
裁判まで行った場合
裁判は判決で必ず結論が出ますし判決には法的な拘束力があります。慰謝料の請求が認められる事実が証明できれば有効な方法です。
しかし、あなたの希望する判決が出なくても、裁判の判決には従わなければならなりません。また、一度判決が出ると不満があっても裁判のやり直しはできません。
裁判所の判決には法的な拘束力がありますが、相手に支払い能力がなければ慰謝料の受け取りが困難である問題もあります。
慰謝料の裁判は弁護士を利用せず本人でも行えますが、弁護士を利用し裁判を進める人が圧倒的多数です。
慰謝料請求の裁判は、手続きが複雑で結論が出るまでに時間が掛かります。また、弁護士は事前に多くの準備をして裁判に挑むので、弁護士費用も和解や調停と比べ高くなります。
慰謝料請求の裁判を弁護士に依頼した場合には、着手金は20~30万円、成功報奨金は獲得金額の10~20%が相場です。
裁判は相手の居住地で行う必要があり、実費や日当が発生する場合があります。
また、裁判は家庭裁判所に収める印紙代、切手代、調書の謄写代を最低でも数万円は必要です。
3 弁護士費用は高い?
弁護士費用の相場を紹介してきましたが、弁護士費用が高いと感じる人もいるかもしれません。
弁護士は形がないサービスの提供が仕事であり、適正な価格が分かり難い特徴があります。
また、日本ではサービスを無料で提供している会社が多く、サービスにお金を払う習慣がない理由もあるでしょう。
弁護士も営利目的で活動する事業主であり、税金で仕事を行っている行政機関とは異なります。そのため、活動に必要な経費に利益を乗せて料金を決まています。
弁護士が安く利用できない理由とお金を払っても弁護士を利用するメリットを紹介します。
3-1 弁護士の業務にはコストが掛かる
弁護士の仕事は、依頼内容や条件だけでなく依頼者の希望も異なるので、画一的な処理ができる仕事ではありません。依頼に合わせたオーダーメイドの対応が必要で手間が掛かる仕事です。
また、依頼者にとっては深刻な問題であり失敗が許されないので、最適な解決策を考え十分な準備が必要な仕事でもあります。
一人の弁護士が同時進行できる数は限られており、一つの依頼で1年近い期間が必要なケースも珍しくありません。そのため、一件の依頼である程度の金額をいただかないと採算が取れないと考えられます。
弁護士事務所は、依頼者には分かり難いさまざまな経費が発生しています。
弁護士だけでは仕事はできないので、一人の弁護士を複数のスタッフが支えて業務を行っておりそれらの人件費が必要です。その他にも、事務所の家賃、事務機器、車、弁護士会の会費などの経費が必要です。
弁護士事務所の経費は個人事務所でも月に100万円は必要と言われており、同時進行できる依頼が限られる弁護士の仕事内容を考えれば、ある程度の金額でなければ経営が成り立ちません。
「弁護士費用=弁護士の利益」ではなく、弁護士費用として依頼者から受け取ったお金から経費を支払い残ったお金が利益です。
3-2 弁護士は高所得な職業?
弁護士は所得が高い職業の代表のようなイメージを持っている人も多いと思います。
2017年における弁護士の平均年収は1,029万円で、職業別ランキングとしては5位となっています。弁護士を上回る年収の職業としては、医師、パイロット、大学教授、公認会計士があります。
この統計からも分かりますが弁護士は高所得の職業ではありますが、大手企業の管理職と比べれば特別に高給を得ている訳ではありません。
司法試験の合格年齢は平均で28歳前後であり、司法試験合格後も下積みの期間が長い職業でもあります。大卒で就職をした場合には22歳から所得を得ていますが、弁護士として十分な所得を得られる年齢は30歳前後と考えられます。
このように、過去の努力や下積み期間を考えれば特別に高額な所得を得ている訳ではないのかもしれません。
ちなみに、企業法務や顧問契約が主な業務の弁護士は年収が高い傾向にあり、離婚や慰謝料請求など単発の民事を中心に活動している弁護士は年収が低い傾向があると言われています。
3-3 結果が出れば高いとは言えない?
弁護士費用が高いのか安いのかの判断は、費用だけでなくリターンを考える必要があります。
弁護士を利用しないと慰謝料が受け取れない場合では、弁護士を利用したら200万円の慰謝料が受け取れるのであれば弁護士費用を60万円支払っても金銭的なメリットがあります。
一方で、慰謝料が少額だったり相手に支払い能力がなければ、弁護士を利用する金銭的なメリットはありません。
慰謝料の金額が弁護士を利用するかの一つの判断材料であり、一般的には100万円以上であれば金銭的なメリットがあるようです。
慰謝料が100万円で弁護士費用が60万円だと経済的利益は40万円ですが、相手は100万円+相手の弁護士費用を支払っているので制裁的な意味を持つ考えもあります。利用者が受ける経済的メリットだけが弁護士を利用する理由ではなく、相手へ制裁を与えたい気持ちが強ければ利用する価値はあるでしょう。
その他、親権の獲得など金銭に変えられない目的があれば、弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。
3-4 弁護士を利用するメリットも多い
弁護士の利用には、結果だけでなくさまざまなメリットがあります。
弁護士を利用する人の多くは、相手との関係性が悪く精神的なストレスを感じています。弁護士に交渉を代理してもらうと、交渉のストレスから解放さえるメリットがあります。また、弁護士を利用すると精神的な安心感を感じる人も多いようです。
弁護士からは法律に関するアドバイスが得られるメリットもあります。
たとえば、離婚後に住宅ローンの連帯保証人になったまだと、相手の支払いができなくなると負債を抱えてしまいます。また、年金や今後受け取る予定の退職金が財産分与の対象と知らなければ、受け取る権利があるお金が受け取れなくなってしまいます。
その他、面会交流を果たさないときの罰則の設定、養育費が受け取れる可能性が高まる構成収書の作成など、法律の専門家からのアドバイスが得られます。
一般の方が知らない法的な知識を弁護士は持っており、これらは弁護士を利用する大きなメリットと言えるでしょう。
相手との関係性が険悪になっていると、通常は問題にならない些細なことでも大きなトラブルに発展する可能性があります。
たとえば、慰謝料の請求が恐喝を受けたとして警察沙汰になってしまい、恐喝に対する慰謝料を請求されてしまう場合もあるようです。
また、お互いが合意して示談書や離婚協議書を作成しても、後になり強要されたので無効と訴えてくる場合も少なくありません。
弁護士はトラブルが起こらないよう細心の注意を払い業務を行っており、後々発生するトラブルを避けられるメリットもあります。
4 まとめ
弁護士の料金体系は、依頼内容で一律の料金が決まっておらず、さまざまな条件や結果により料金が異なる料金体系です。
また、一定の料金で最後まで対応してくれる料金体系ではなく、和解で解決した場合と裁判を行った場合では支払総額が異なります。その他、得られた結果や金銭で成功報酬金が発生しますし、業務に必要な諸経費が別途必要になる契約が一般的です。
そのため、弁護士費用は少し複雑で、料金の相場が分かり難い特徴があります。
弁護士費用の目安は、法律相談は1時間に付き5,000円~15,000円、示談書や離婚協議書の書類作成のみの依頼は5万円~10万円が相場です。
離婚問題の解決を弁護士に依頼すると、協議で合意できれば30万円~60万円、調停では40万円~80万円、裁判では60万円~120万円が相場のようです。
慰謝料の請求を弁護士に依頼すると、着手金は10~20万円、成功報奨金は獲得金額の10~20%で、獲得できる慰謝料の金額によって異なります。
ただし、条件が異なれば料金も異なりますし弁護士によっても料金は異なります。
弁護士を利用するとある程度の費用は必要です。
弁護士費用を上回る金銭的メリットがあるのか?お金を掛けても手に入れたいのかを考えてみましょう。また、弁護士を利用すると交渉のストレスから解放されたり、トラブルを避けられるメリットもあります。
弁護士を利用するメリットと利用しないリスクを考え、弁護士を利用するメリットを感じられれば利用する価値はあるでしょう。